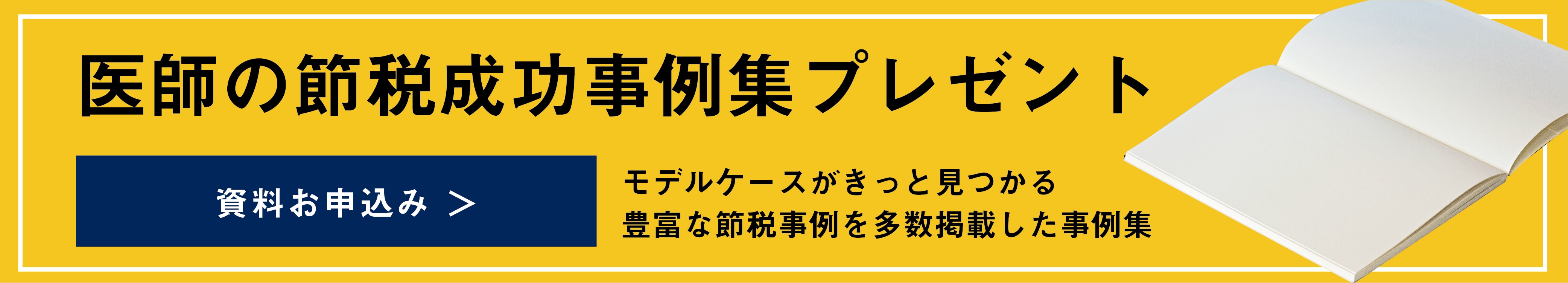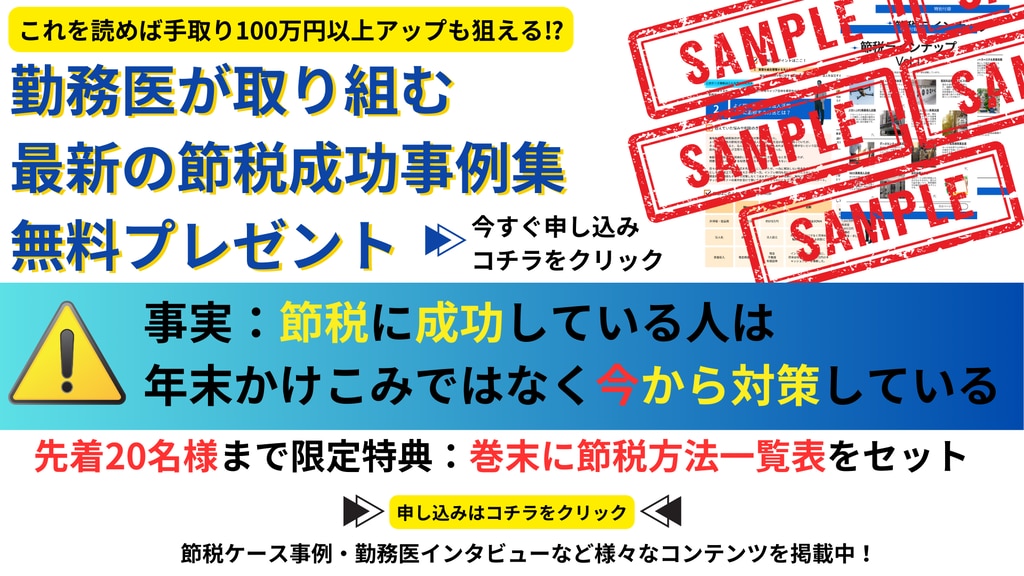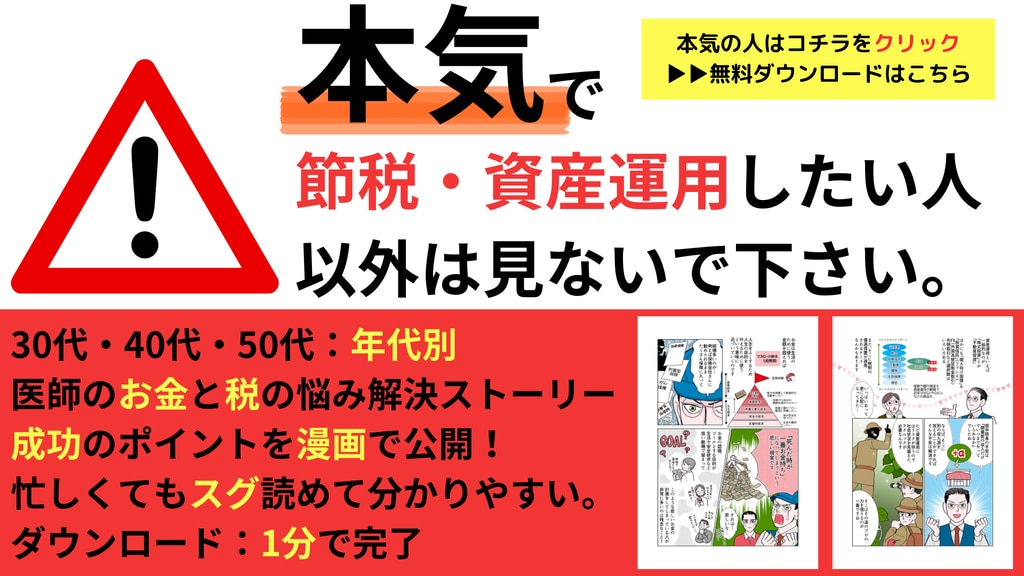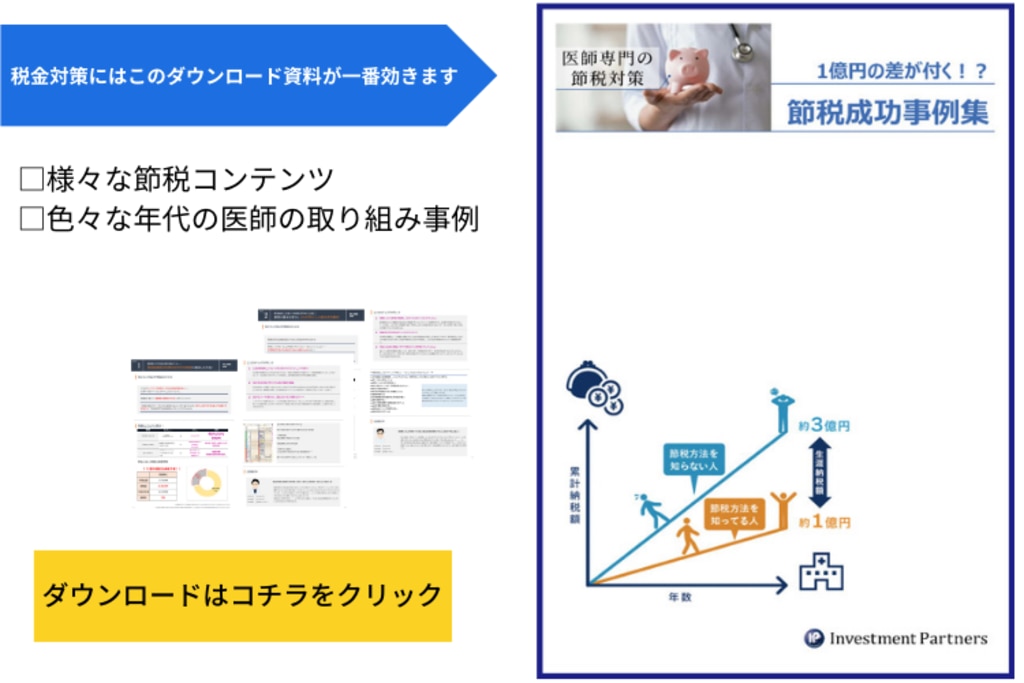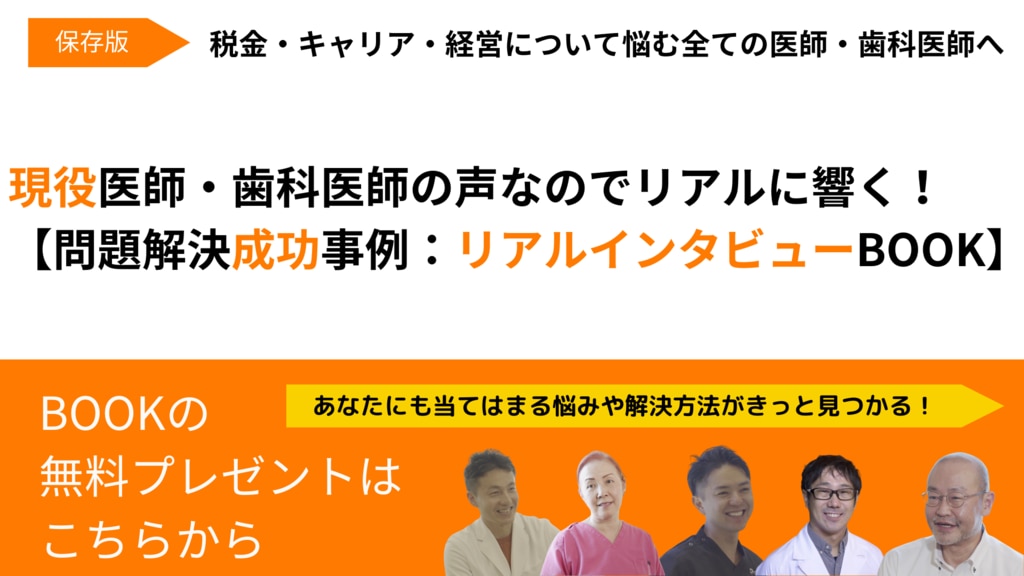医師が税務調査に備えるためのチェックリスト
税務調査は、法人・個人を問わず、すべての事業者が対象となる可能性があります。
医療機関も例外ではなく、保険診療報酬や自由診療収入の計上時期、交際費や外注費の妥当性など、業種特有の確認ポイントがあります。
ただし、税務調査は決して恐れるものではありません。日頃から適切な会計処理と書類管理を行い、正しく申告していれば問題なく対応できます。
本記事では、医師が税務調査に備えるために押さえておくべきポイントをチェックリスト形式で詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.税務調査の基礎知識
- 1.1.税務調査とは
- 1.2.税務調査の実施確率と対象となりやすい医療機関
- 1.3.税務調査の流れ
- 2.医師・医療機関に特有の指摘されやすいポイント
- 3.税務調査に備えて準備すべき書類
- 4.加算税・延滞税のペナルティ
- 4.1.加算税の種類と税率
- 4.2.延滞税
- 4.3.ペナルティを受けないために
- 5.税務調査当日の対応ポイント
- 5.1.調査前の準備
- 5.2.調査当日の注意点
- 5.3.やってはいけないこと
- 6.税務調査を受けにくくするための日常対策
- 7.税務調査後の対応
- 7.1.指摘事項への対応
- 7.2.修正申告が必要な場合
- 7.3.指摘に納得できない場合
- 8.まとめ
税務調査の基礎知識
税務調査の仕組みや実施確率、医療機関が対象になりやすい理由など、基本的な知識を確認しておきましょう。
税務調査とは
税務調査とは、国税庁や税務署が納税者の申告内容が正確かどうかを確認するために実施する調査のことです。日本は申告納税制度を採用しているため、納税者自身が所得や税額を計算して申告します。
税務調査は、この申告内容に誤りがないか、適正な納税が行われているかを確認することで、公平な課税を実現することを目的としています。
税務調査の種類は「任意調査」と「強制調査」の2つです。一般的な税務調査のほとんどは任意調査に該当します。任意調査は、国税通則法に基づいて実施され、実地調査の場合は原則として事前に通知が行われます。納税者は調査日程の調整が可能で、都合が悪い場合は変更を申し出ることができます。
一方、強制調査は国税局査察部が実施するもので、裁判所の令状に基づいて行われます。これは悪質な脱税が疑われる場合に限定されており、一般の医療機関が対象となることはほとんどありません。
なお、任意調査といっても、正当な理由なく調査を拒否したり、帳簿の提示を拒んだりすると、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
税務調査の実施確率と対象となりやすい医療機関
国税庁が公表している統計データによると、税務調査の実施確率は以下の通りです。
法人の場合:令和5事務年度のデータでは、法人税の申告件数約318万件に対し、税務調査の実施件数は約5万9,000件でした。これは約1.9%の確率に相当します。
個人開業医の場合:令和5事務年度のデータでは、申告納税額があった個人の確定申告件数は約669万件で、税務調査の実施件数は約4万8,000件でした。これは約0.7%の確率です。個人開業医もこの中に含まれます。ただし「簡易な接触」を合わせると、60万5,000件となっているため、注意が必要です。
また、医師・医療機関は一般の事業者と比較して税務調査の対象となりやすい傾向があります。令和5事務年度の統計では、内科医が1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種として8位に入っています。
医師が税務調査の対象になりやすい理由としては、以下の点が挙げられます。
自由診療収入の把握が重要
保険診療は比較的お金の流れが明確ですが、美容診療、健康診断、予防接種などの自由診療収入は適切に計上されているか確認が必要です。自由診療の割合が高い診療科では、収入の適正計上について特に注意が必要です。
現金収入が多い
患者からの窓口負担金など、現金でのやり取りが多いため、収入の計上漏れが疑われやすい業種です。
高額所得者が多い
医師は一般的に所得水準が高く、税務調査による税収確保の効率が良いため、対象として選ばれやすい傾向があります。
税務調査の流れ
税務調査は以下のような流れで実施されます。
①事前通知: 原則として、税務調査の実施前に納税者または税理士に対して事前通知が行われます。通知は電話で行われることが一般的で、調査の2~3週間前に連絡があります。事前通知では、調査開始日時、調査場所、調査の目的、調査対象となる税目や期間などが伝えられます。
②日程調整: 事前通知を受けたら、税務署の担当者と調査日程を調整します。業務の都合や顧問税理士のスケジュールを考慮して日程を決めることができます。税務調査は通常2~3日間かけて行われるため、まとまった時間が確保できる日を選びましょう。
③準備期間: 調査当日までに必要な書類を準備します。税理士がいる場合は、事前に打ち合わせを行い、想定される質問への回答を準備しておくことが重要です。
④実地調査: 調査当日、調査官が事業所に訪問します。一般的に調査官は1~2名です。午前中は事業の概要や経営状況についてのヒアリングが行われ、午後から帳簿や書類の確認作業に入ります。調査は2~3日程度続くことが多く、初日の終わりに翌日確認したい資料を依頼されることもあります。
⑤調査結果の通知: 調査終了後、調査官から指摘事項があるかどうかの説明があります。指摘事項がない場合は「申告是認」となり、税務調査は終了します。指摘事項がある場合は、その内容について説明を受けます。
⑥修正申告または更正: 指摘事項に納得した場合は修正申告を行い、追加の税額と加算税・延滞税を納付します。指摘内容に納得できない場合は、税理士を通じて交渉するか、税務署が職権で更正処分を行うことになります。
医師・医療機関に特有の指摘されやすいポイント
医療機関の税務調査では、業種特有の指摘事項があります。以下のチェックリストを確認し、日頃から適切な処理を心がけましょう。
収入計上の適正性
医療機関の収入計上で最も重要なのは、計上時期と計上漏れの防止です。税務調査で指摘されやすいポイントを確認しましょう。
【チェック項目】
・保険診療報酬の計上時期(入金時ではなく診療時)
保険診療報酬は、発生主義の原則に基づき、実際に入金された日ではなく、診療を行った日(役務提供日)に売上として計上します。診療報酬は翌々月に入金されることが一般的ですが、売上の計上は診療月に行い、入金までは「未収金」として処理します。
・自由診療収入の計上漏れ(美容診療、健康診断、予防接種、自賠責保険診療等)
自由診療は税務調査で特に注目される項目です。美容診療、健康診断、予防接種、自賠責保険による診療、検査証明書発行料などの自由診療収入が適切に計上されているか確認しましょう。これらは現金で受け取ることも多いため、計上漏れが疑われやすい項目です。
・物販収入(医療器具、サプリメント等)の計上
医療器具やサプリメント、化粧品などの物販を行っている場合、これらの収入も適切に計上する必要があります。特に美容クリニックでは物販収入の比率が高くなるため、在庫管理と売上計上の整合性が確認されます。
・治験受託収入の計上
製薬会社から受け取る治験受託収入も売上として計上する必要があります。
・クレジットカード決済の売上計上時期
クレジットカードで診療費が支払われた場合も、売上の計上日は実際の入金日ではなく、診療を行った日です。会計処理では、決済手数料を差し引いた金額ではなく、総額を売上として計上し、手数料は支払手数料として経費処理します。なお、クレジットカード決済手数料は、加盟店が信販会社に支払う場合、消費税法上は非課税取引となります。
・休日/夜間診療加算の未収金処理
休日や夜間診療の加算報酬が発生した場合や、行政の検診などによる収入も、正しく未収金処理を行いましょう。
経費計上の妥当性
経費の計上については、事業との関連性が厳しくチェックされます。私的な費用を経費として計上していないか、以下の項目を確認しましょう。
【チェック項目】
・交際費の妥当性(領収書に「誰と」「目的」を記載)
医療機関では学会参加や医師との情報交換など、交際費が発生しやすい業種です。しかし、友人との飲食代を経費として計上していないか確認されます。領収書には必ず「誰と」「何の目的で」支出したかをメモしておきましょう。取引先や医療関係者との会食であることが説明できれば問題ありません。
・学会参加費用の事業関連性
学会参加費、旅費、宿泊費は事業に必要な経費として認められます。ただし、学会参加に家族が同伴した場合の家族分の費用や、学会の前後に観光を行った場合の費用は経費として認められないため、明確に区分しておく必要があります。
・個人消費と事業費の按分(水道光熱費、通信費、車両費等)
個人事業主の場合、自宅兼診療所のケースでは、水道光熱費、通信費、家賃などを事業用と私用で按分する必要があります。按分割合は使用実態に基づいて合理的に決定し、その根拠を説明できるようにしておきましょう。
・高級車など私的使用が疑われる資産の経費計上
高級車を購入し、主に個人的な用途で使用しているにもかかわらず、全額を事業の経費として計上している場合、税務調査で指摘されます。車両を事業とプライベートの両方で使用している場合は、使用割合に応じて按分が必要です。
・消耗品の使途確認
事務用品や医療消耗品が、実際に事業で使用されているか確認されます。個人的な目的で購入したものを経費として計上していないか注意しましょう。
棚卸資産の管理
医薬品や医療材料を多く抱える医療機関では、棚卸資産の管理が重点的に調査されます。
【チェック項目】
・医薬品・医療材料の棚卸の正確性
期末時点での在庫を正確に計上する必要があります。棚卸を適切に行わないと、経費が過大に計上され、所得が過少に申告されることになります。
・棚卸表の計算式の確認
Excelなどで棚卸表を作成する場合、品名・単価・数量と計算式を正確にメンテナンスする必要があります。計算式の誤りにより金額が間違っていないか、税務調査では必ず確認されます。
・期末棚卸の実施記録
期末に実際に棚卸を実施したことを示す記録(棚卸実施日、実施者、確認者など)を残しておきましょう。
外注費の実態確認
外注費は、給与として処理すべきものが含まれていないか、架空の外注費ではないかなど、税務調査で詳しく確認される項目です。
【チェック項目】
・外注先の実在性確認
外注先が実在し、実際に業務を委託していることを証明できる資料を保管しましょう。契約書、請求書、業務報告書などが重要な証拠となります。
・給与として処理すべきものの判定
外注費として処理している支払いが、実質的には雇用関係にあり、給与として処理すべきではないか確認されます。指揮命令関係の有無、勤務時間の拘束性、報酬の計算方法などから総合的に判断されます。
・外注費の水増しがないことの確認
実際の作業内容に対して外注費の金額が適正か、水増しして計上していないか確認されます。
税務調査に備えて準備すべき書類
税務調査では、過去の取引内容を証明する書類の提示を求められます。必要な書類を適切に保管しておくことが重要です。
必須書類リスト
税務調査で提示を求められる可能性のある書類を、あらかじめ整理しておきましょう。
税務調査は一般的に過去3年分が対象となります。法律上は5年まで遡ることができ、申告に誤りが見つかった場合などは5年分に延長されることがあります。さらに、重大な問題が発見された場合は最大7年分まで遡って調査されることがあります。
なお、帳簿書類の法定保存期間は原則7年間(法人の場合)ですので、7年分の書類を適切に保管しておくことが重要です。
【基本書類】
※法定保存期間は原則7年間
総勘定元帳、仕訳帳
現金出納帳
預金通帳(事業用・個人用)
売上帳、仕入帳
固定資産台帳
決算書、確定申告書の控え
源泉徴収簿
給与台帳
【取引関係書類】
※法定保存期間:法人は7年間、個人(青色申告)は5年間
請求書(発行分・受領分)
領収書(全ての経費に関するもの)
契約書(リース契約、業務委託契約等)
レセプト(診療報酬明細書)
棚卸表(期末在庫の記録)
【医療法人特有の書類】
医療法人の場合は、上記に加えて以下の書類も準備しておきましょう。
社員総会議事録
理事会議事録
定款
組織図
病院案内、パンフレット
帳簿書類の保存期間
帳簿書類は法律で定められた期間、保存する義務があります。保存期間を守らない場合、青色申告の承認が取り消されるなどのペナルティが科される可能性があります。
法人の保存期間
法人税法により、帳簿書類はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間の保存が義務付けられています。
ただし、青色申告で欠損金の繰越控除を行っている場合は、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要です。
個人事業主の保存期間
青色申告の場合、原則として帳簿や決算関係書類、現金預金取引等関係書類は7年間、その他の取引関係書類(請求書、領収書など)は5年間の保存が必要です。
ただし、前々年分の事業所得又は不動産所得の金額が300万円以下の場合、現金預金取引等関係書類は5年間の保存で足ります。
白色申告の場合は、法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)は7年間、その他の帳簿や書類は5年間の保存が必要です。
保存期間の起算日
保存期間の起算日は、確定申告書の提出期限の翌日からです。法人の場合、確定申告書の提出期限は原則として「各事業年度終了の日の翌日から2か月以内」です。個人の場合は、毎年3月15日が確定申告の提出期限となりますので、その翌日である3月16日から起算します。
例えば、3月決算の法人が2024年3月期の決算を行った場合、確定申告の提出期限は2024年5月31日となり、その翌日である2024年6月1日から7年間(または10年間)、つまり2031年5月31日(または2034年5月31日)まで保存する必要があります。
なお、保存期間は税法上の最低期間です。帳簿や決算書などの重要な書類は、保存期間が過ぎても保管しておくことをお勧めします。
書類整理のポイント
税務調査では、調査官から突然特定の書類の提示を求められることがあります。すぐに対応できるよう、日頃から書類を整理しておきましょう。
帳簿書類は年度別、月別に整理し、ファイリングしておきます。領収書は月ごとにまとめ、封筒などに入れて保管すると便利です。
領収書を見せてくださいと言われたときに、すぐに取り出せるようにしておくことが重要です。探すのに時間がかかると、調査官に不信感を与える可能性があります。
会計ソフトのデータや電子取引のデータは、定期的にバックアップを取っておきましょう。電子帳簿保存法に基づき、電子取引のデータは電子のまま保存する必要があります。
加算税・延滞税のペナルティ
税務調査の結果、申告内容に誤りが見つかり、追加で税金を納めることになった場合、本来の税額に加えて加算税や延滞税が課されます。
加算税の種類と税率
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類があります。それぞれの税率と適用要件は以下の通りです。
【加算税の種類と税率】
重加算税の対象となる行為例: 売上の除外、架空仕入の計上、帳簿の改ざんなど、意図的に所得を隠蔽したと認められる場合。単純な計算ミスや記帳ミスでは重加算税は課されません。
延滞税
税金を期限までに納付しなかった場合、利息に相当する延滞税が日割りで課されます。
- 納期限の翌日から2か月以内:年2.4%(令和4年1月1日から令和7年12月31日まで)
- 納期限の翌日から2か月を経過した日以降:年8.7%(令和4年1月1日から令和7年12月31日まで)
延滞税の税率は年度によって変動します。なお、重加算税が課される場合、通常の加算税とは異なり、延滞税の計算期間が1年を超えても延滞税が課され続けるため、金額が大きくなる可能性があります。
ペナルティを受けないために
加算税や延滞税といったペナルティを受けないためには、以下の原則を守ることが重要です。
正確な記帳と申告
日々の取引を正確に記帳し、適正な申告を行うことが基本です。不明な点があれば、自己判断せずに税理士に相談しましょう。
私的費用と事業費の明確な区分
個人的な支出を事業の経費として計上しないよう、明確に区分します。特に交際費、車両費、通信費などは注意が必要です。
証憑書類の適切な保管
領収書、請求書などの証憑書類は、法定保存期間にわたって適切に保管します。証憑書類がなければ、経費として認められない可能性があります。
不明点は税理士に相談
税務上の判断に迷う場合は、必ず税理士に相談して適切な処理方法を確認しましょう。自己判断で誤った処理を行うと、後で修正が必要になります。
税務調査当日の対応ポイント
税務調査の当日は、適切な対応を心がけることで、調査をスムーズに進めることができます。
調査前の準備
顧問税理士がいる場合は、調査前に必ず打ち合わせを行います。想定される質問や、過去の申告内容で気になる点について確認し、回答を準備しておきましょう。
事業の概要、収入の内訳、主要な経費の内容など、基本的な質問に対する回答を準備しておきます。特に前年度から大きく変動した項目については、その理由を説明できるようにしておきましょう。
提示を求められる可能性のある書類が揃っているか、最終確認を行います。不足している書類があれば、可能な限り準備しておくことが大切です。調査官が作業できる場所を確保し、帳簿や書類を広げて確認できる十分なスペースと、机、椅子を用意しましょう。
調査当日の注意点
調査官からの質問には、正直に回答することが最も重要です。虚偽の説明をすると、重加算税が課される可能性があります。また、曖昧な回答は調査官に不信感を与えるため、分からないことは「分からない」とはっきり伝えましょう。
即答できない質問や、確認が必要な事項については、その場で無理に答えようとせず、「確認して後日回答します」と伝えて問題ありません。税理士に相談してから回答することもできます。
税務調査は法律に基づく正当な手続きですので、調査官の指示には協力的に対応しましょう。帳簿や書類の提示を求められたら、速やかに対応します。
質問されたことに対して正直に答えることは重要ですが、質問されていない事項について自ら積極的に情報を提供する必要はありません。余計な情報が新たな疑問を生む可能性もあります。
税理士が立ち会っている場合は、回答に迷ったときや、調査官の指摘内容が理解できないときは、その場で税理士に相談しましょう。
やってはいけないこと
以下に紹介する行為は、調査を長引かせたり、重加算税の対象となったりする可能性があるため、絶対に避けましょう。
事実と異なる説明をすることは、最も避けるべき行為です。仮装・隠蔽と判断されると、重加算税が課される可能性があります。
税務調査が決まってから帳簿を書き換えたり、領収書を破棄したりする行為は、重大な違反行為です。絶対に行ってはいけません。
正当な理由なく調査を拒否したり、帳簿の提示を拒んだりすると、罰則が科される可能性があります。任意調査といっても、協力義務があることを理解しましょう。
調査官の指摘に対して感情的になったり、威圧的な態度をとったりすることは避けましょう。冷静に対応することが重要です。
税務調査を受けにくくするための日常対策
税務調査の対象となる確率を下げるためには、日頃から適正な会計処理を行い、申告内容に不審な点がないようにすることが重要です。
適正な会計処理
日々の取引は、できるだけ早く記帳しましょう。時間が経つと記憶が曖昧になり、誤った処理をしてしまう可能性があります。遅くとも月次で記帳を完了させることをお勧めします。
現金の出入りを正確に記録し、現金出納帳の残高と実際の手元現金が一致するよう管理します。現金管理が適切でないと、収入の計上漏れが疑われる可能性があります。
月次または四半期ごとに帳簿をチェックし、誤りがないか確認します。前年同期との比較や、予算との対比を行うことで、異常値を早期に発見できます。
税理士との連携
顧問税理士がいる場合は、定期的に面談を行い、事業の状況や会計処理について相談しましょう。税理士の関与があることは、適正な申告を行っている証左となります。
書面添付制度(税理士法第33条の2)は、税理士が申告書の作成にあたって確認した事項を書面にして添付する制度です。
この制度を活用すると、税務調査の前に税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が設けられ、その段階で調査官の疑問が解消されれば、税務調査が省略されることがあります。
税務上の判断に迷う取引があった場合は、後回しにせず、その都度税理士に相談して適切な処理方法を確認しましょう。
内部管理体制の整備
経理処理のルールを明文化し、職員間で共有します。誰が処理しても同じ結果になるよう、標準化しておくことが重要です。
経理を担当する職員に対して、適切な会計処理の方法を教育します。領収書の保管方法、経費の区分など、基本的なルールを徹底しましょう。
経理処理は一人で完結させず、別の担当者がチェックする体制を整えます。ミスの発見や不正の防止に効果的です。
申告内容の精査
自院の収益性や経費率を、同規模の同業他社と比較してみましょう。大きく乖離している項目があれば、その原因を確認し、説明できるようにしておきます。
前年度と比較して大きく変動した項目については、その理由を明確にしておきます。売上の増減、特定の経費の増減などについて、合理的な説明ができるようにしましょう。
通常では考えにくい数値(極端に高い経費率、連続する赤字など)がある場合、その原因を確認し、必要に応じて申告前に税理士に相談します。
税務調査後の対応
税務調査の結果、指摘事項があった場合の対応方法を確認しておきましょう。
指摘事項への対応
調査官から指摘を受けた場合、その内容を正確に理解することが重要です。不明な点があれば、その場で質問して明確にしましょう。
指摘内容について、税理士と協議します。指摘が妥当かどうか、反論の余地がないかを検討します。
指摘内容に納得できる場合は修正申告を行いますが、納得できない場合は反論することも可能です。ただし、明らかに誤りがある場合は、素直に認めて修正申告を行う方が、結果的にペナルティを軽減できることもあります。
修正申告が必要な場合
指摘事項を認めた場合は、速やかに修正申告書を作成し、提出します。
修正申告書の提出後、不足していた税額、延滞税、加算税を納付します。納付が遅れると、さらに延滞税が加算されていくため、できるだけ早く納付しましょう。
同じ誤りを繰り返さないよう、原因を分析し、再発防止策を講じます。会計処理のルールを見直したり、チェック体制を強化したりすることが考えられます。
指摘に納得できない場合
指摘内容に納得できない場合は、税理士を通じて調査官に反論や説明を行います。法令の解釈や事実認定について、異なる見解を主張することは認められています。
税務署の処分に不服がある場合、不服申立て(再調査の請求または審査請求)を行うことができます。不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
反論する場合は、それを裏付ける証拠資料を準備します。契約書、メール、メモなど、事実関係を証明できる資料を整理しておきましょう。
まとめ
税務調査は、適切な準備をしていれば恐れるものではありません。日頃から正確な記帳と適正な申告を行い、必要な書類を保管しておけば、自信を持って調査に対応できます。
医師・医療機関として押さえるべき重要ポイントは、自由診療収入を含む全収入の適正計上、交際費・外注費など指摘されやすい経費の証跡管理、帳簿書類の7年間保存、そして税理士との連携強化です。
税務調査の事前通知を受けた場合は、まず顧問税理士に相談し、本記事のチェックリストを活用して準備を進めましょう。
また、税務調査は過去の申告内容を見直す良い機会でもあります。指摘事項があった場合は、それを今後の改善につなげ、より適正な会計処理と申告を目指しましょう。
※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。 |