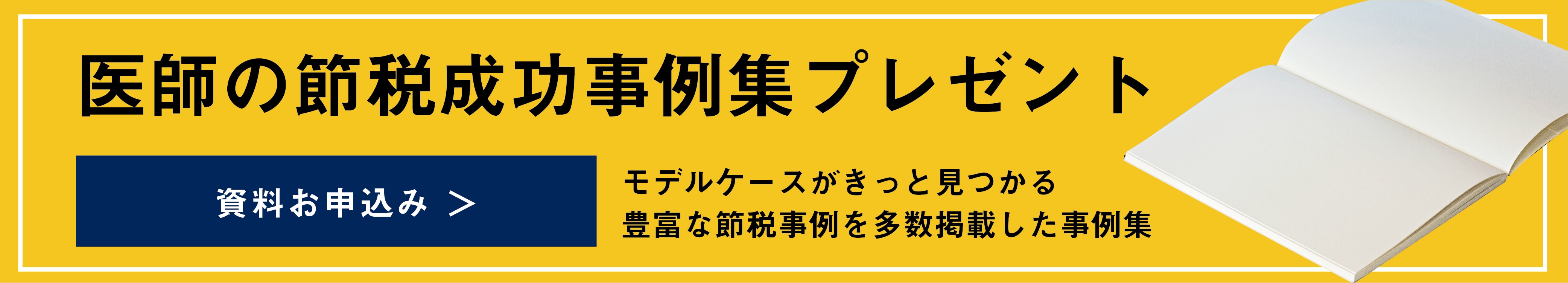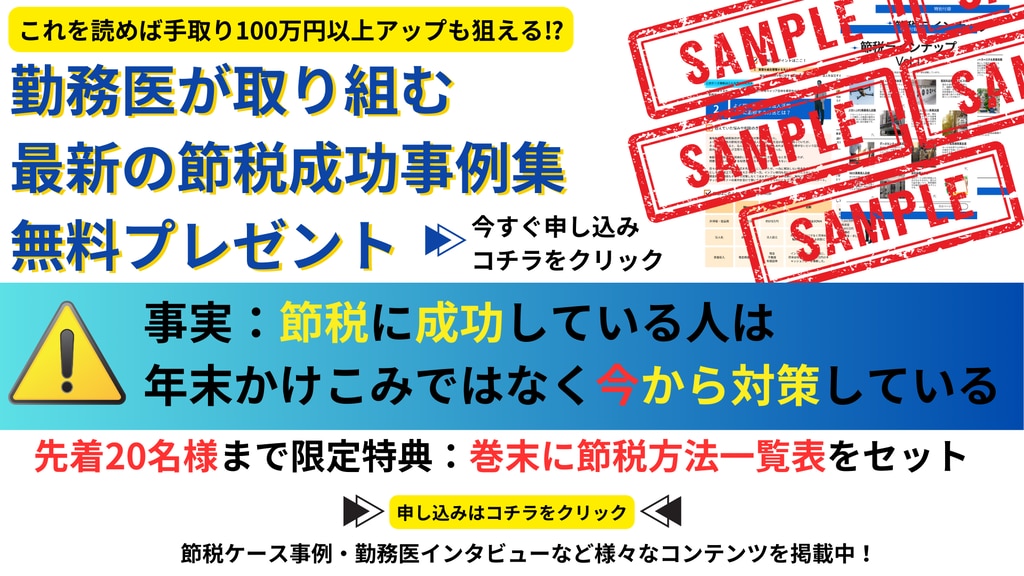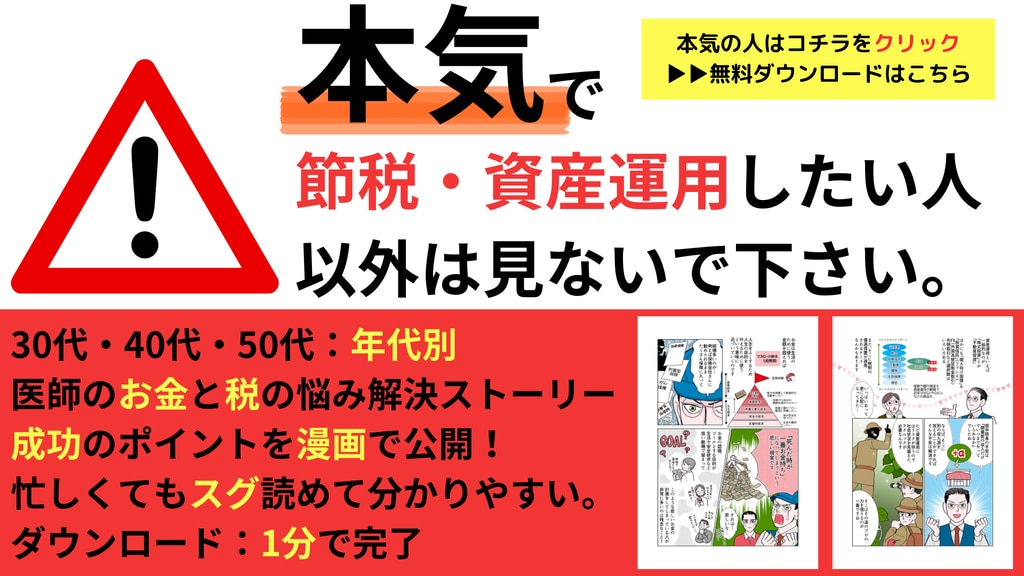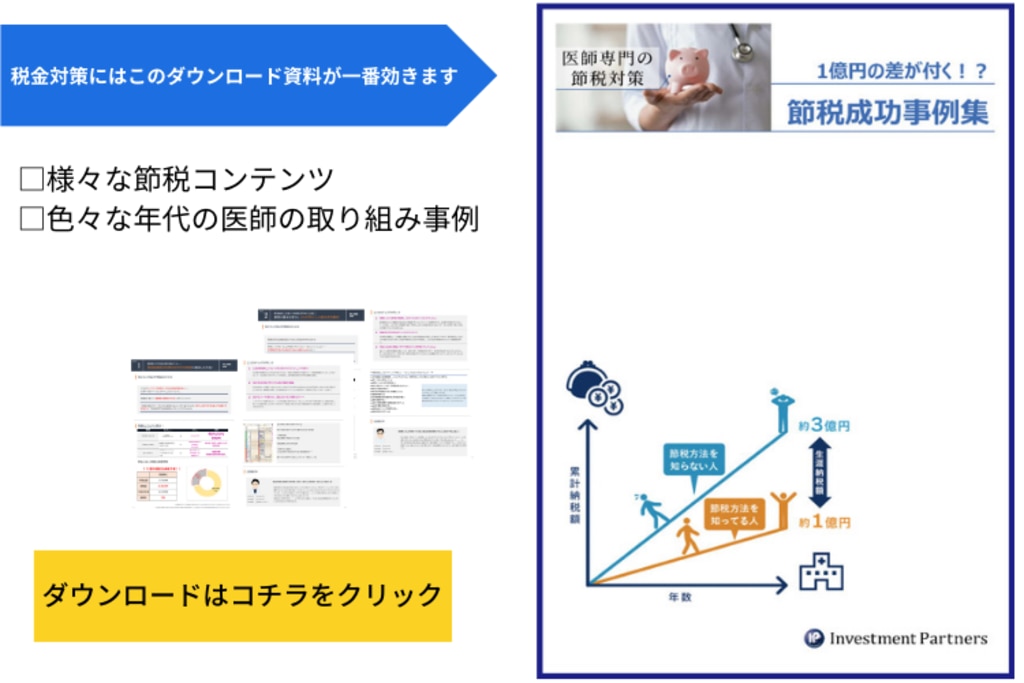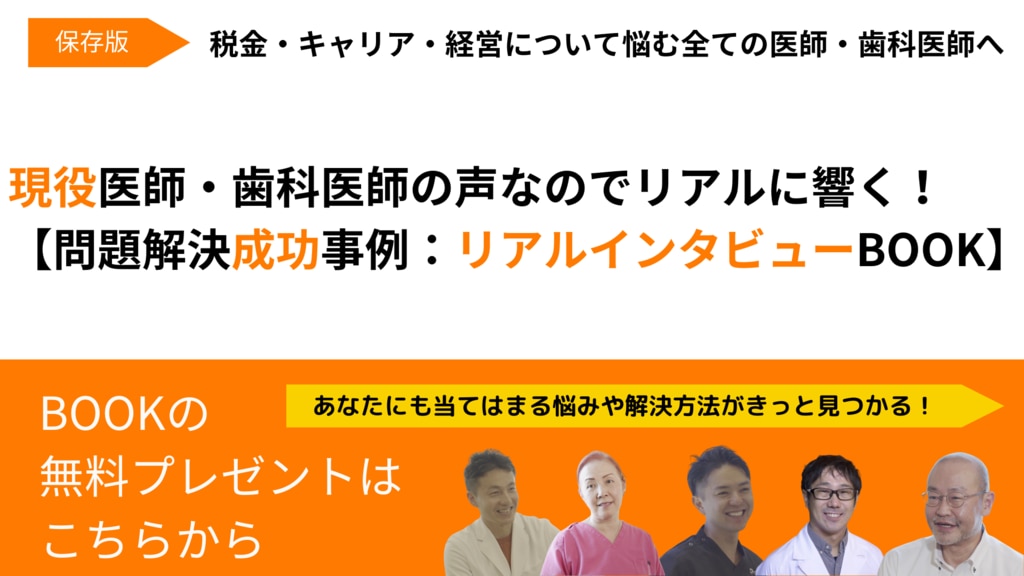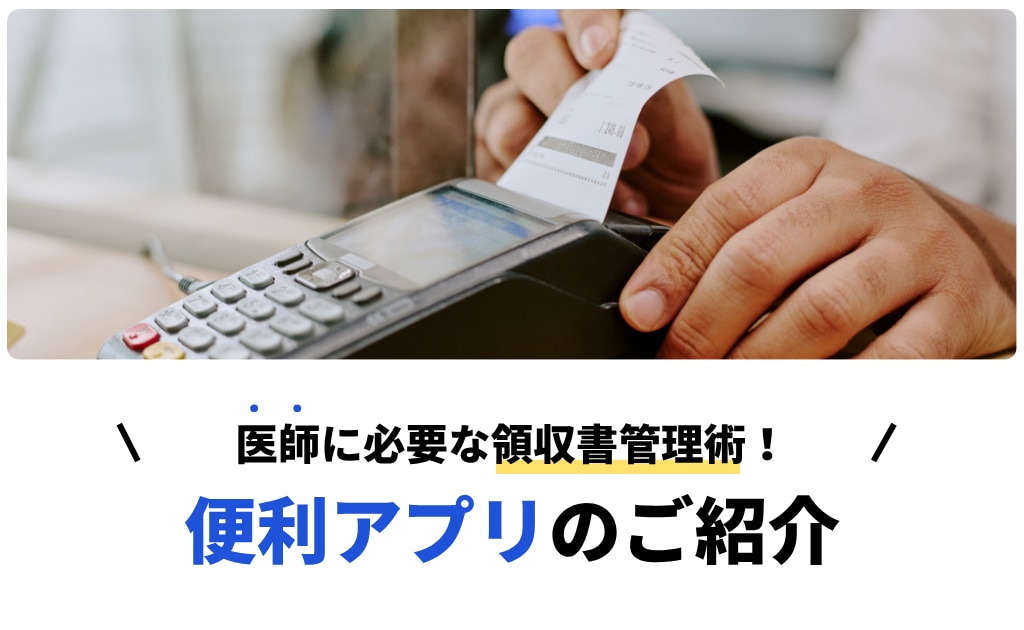
医師に必要な領収書管理術と便利アプリ
開業医として活動する場合、個人事業主として確定申告を行う必要があります。適切な経費管理は節税の基本であり、その中核を担うのが領収書の管理です。
本記事では、医師が押さえておくべき領収書管理の基礎知識から、業務を効率化する便利なアプリまで、実務に即した情報をお届けします。
目次[非表示]
- 1.医師にとっての領収書管理の重要性
- 2.領収書の法定保存期間と基本管理
- 3.電子帳簿保存法への対応
- 3.1.電子帳簿保存法の概要
- 3.2.電子取引データ保存の義務化
- 3.3.スキャナ保存の活用
- 4.医師におすすめの領収書管理アプリ
- 4.1.マネーフォワード クラウド経費
- 4.2.楽楽精算
- 4.3.弥生シリーズ
- 4.4.freee会計
- 4.5.ジンジャー経費
- 5.アプリ選びのポイント
- 5.1.電子帳簿保存法への対応
- 5.2.操作の簡便性
- 5.3.会計ソフトとの連携
- 5.4.コストパフォーマンス
- 5.5.サポート体制
- 6.領収書管理の実務ポイント
- 7.領収書がない場合の対処法
- 8.まとめ
医師にとっての領収書管理の重要性
開業医は個人事業主として事業所得の申告が必要です。
勤務医時代は源泉徴収により税務手続きが完了していましたが、開業後は自ら確定申告を行わなければなりません。その際、経費として計上できる支出の証明として、領収書が重要な役割を果たします。
医療機関の経営では多岐にわたる経費が発生するでしょう。医療機器の購入費、医薬品や診療材料の仕入れ、施設の賃借料、スタッフの給与、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、研修参加費、専門書籍代など、これらすべての支出を適切に記録し、領収書を保管することで正確な所得計算が可能になります。
経費の適切な管理は税務対応だけでなく、経営判断の材料としても重要です。どの分野にどれだけの費用がかかっているかを把握することで、経営の効率化や改善点の発見につながります。
例えば、医薬品の仕入れコストが予算を超過していれば仕入れ先の見直しを検討できます。また、広告宣伝費の効果を測定することで費用対効果の高い施策に注力できるでしょう。
さらに、開業医は租税特別措置法の特例により、社会保険診療報酬に係る経費を概算で計上できる場合があります。ただし、実額での経費計上を選択する場合や、自由診療の割合が高い場合は、すべての経費について領収書に基づく正確な記録が求められます。
領収書管理は単なる税務対応にとどまらず、健全な医療機関経営の基本です。
領収書の法定保存期間と基本管理
領収書には法定保存期間が定められており、適切な整理・保管方法を理解することが重要です。ここでは保存期間の基本ルール、受領時の確認事項、整理・保管方法、経費計上時の注意点について解説します。
保存期間の基本
領収書の保存期間は所得税法で定められており、確定申告の種類によって異なります。国税庁によれば、青色申告を行う個人事業主は原則として7年間の保存が必要です。ただし、前々年分の所得が300万円以下の場合は5年間の保存で足ります。
保存期間の起算日は領収書を受け取った日ではなく、確定申告書の提出期限の翌日からです。個人事業主の確定申告提出期限は毎年3月15日(土日祝日の場合は翌営業日)であるため、例えば2024年に受領した領収書は、2025年3月15日の翌日から7年間、つまり2032年3月15日まで保管する必要があります。
白色申告の場合、領収書の保存期間は5年間です。ただし、法定帳簿の保存期間は青色申告と同様に7年間であることから、混同を避けるため、領収書も7年間保存しておくことが推奨されます。
また、消費税の課税事業者の場合、仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書(インボイス)に該当する領収書は7年間の保存が義務付けられています。税務調査は過去7年分について実施されることが一般的であることからも、7年間の保存を基本と考えましょう。
受領時の確認事項
領収書を受け取った際は、必要事項が記載されているかを即座に確認することが重要です。
宛名(医療機関名または個人名)、日付、金額、但し書き(購入内容)、発行者の名称と住所が明記されているかをチェックしてください。
特に但し書きは「お品代」などの曖昧な表現ではなく、具体的な内容が記載されているものが望ましいといえます。税務調査の際に経費の妥当性を説明する根拠となるためです。
整理・保管方法
領収書は月別、勘定科目別などの一定のルールに従って整理します。
一般的には、月ごとにファイリングし、さらに勘定科目ごとに分類する方法が管理しやすいでしょう。A4サイズの台紙に領収書を貼付し、ファイルに綴じる方法が一般的です。
保管場所は施錠可能な場所がのぞましく、7年間分の領収書は相当な量になるため、保管スペースの確保も計画的に行う必要があります。
経費計上の注意点
医師が経費として計上できるのは、事業に直接関連する支出に限られます。医療機器の購入費や減価償却費、医薬品や診療材料の仕入れ費用、施設の賃借料、光熱費、通信費、広告宣伝費、スタッフの給与、研修参加費、専門書籍代などが該当します。
一方、個人事業主本人の健康診断費用や医療費は原則として経費にはなりません。ただし、医療費控除の対象となる可能性があるため、領収書は保管しておきましょう。
自宅兼診療所の場合、水道光熱費や通信費は事業用と家事用に按分する必要があります。按分比率は床面積や使用時間などの合理的な基準に基づいて算定してください。
電子帳簿保存法への対応
2024年1月から電子取引データの保存が義務化されており、医師も対応が求められます。ここでは電子帳簿保存法の概要、電子取引データ保存の義務化、スキャナ保存の活用方法について説明します。
電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際の要件を定めた法律です。主に3つの区分があります。
「電子帳簿等保存」は会計ソフトで作成した帳簿を電子保存するもの、「スキャナ保存」は紙の領収書をスキャンして電子保存するもの、「電子取引データ保存」はメールやウェブサイトで受け取った領収書を電子保存するものです。
電子取引データ保存の義務化
メールで受信した請求書や、クレジットカード会社のウェブサイトからダウンロードした利用明細など、電子的にやり取りされた取引情報は、電子データのまま保存しなければなりません。印刷して紙で保存することは原則として認められていません。
保存にあたっては「真実性の確保」と「可視性の確保」が要件となります。
真実性の確保とは、データの改ざん防止措置を講じることを意味します。可視性の確保とは、税務調査の際に速やかにデータを提示できるようにすることです。検索機能を備え、取引年月日、取引金額、取引先で検索できるようにする必要があります。
スキャナ保存の活用
紙で受け取った領収書をスキャンして電子データとして保存することも可能です。スキャナ保存は任意であり、実施する場合は一定の要件を満たす必要があります。解像度は200dpi以上、カラー画像での読み取りが原則で、入力期間は最長2か月と7営業日以内、タイムスタンプの付与、検索機能の確保などが求められます。
2022年の電子帳簿保存法改正により、スキャナ保存の要件が大幅に緩和されました。税務署への事前承認が不要になり、任意のタイミングで開始できるようになっています。要件を満たしてスキャナ保存を行えば、スキャン後の紙の原本は廃棄できるため、保管スペースの削減が可能です。
医師におすすめの領収書管理アプリ
領収書管理の効率化には、デジタルツールの活用が有効です。ここでは、個人事業主の医師が利用しやすい主要なアプリを5つ紹介します。
マネーフォワード クラウド経費
東証プライム市場に上場する株式会社マネーフォワードが提供する経費精算システムです。
スマートフォンで領収書を撮影するだけで、OCR機能により日付や金額、支払先を自動で読み取ります。
電子帳簿保存法のスキャナ保存ソフト法的要件認証を経費精算システムとして国内第1号で取得しており、法令対応の面でも安心です。クレジットカードや電子マネーの明細を自動取得できるため、キャッシュレス決済の経費も漏れなく記録できます。
楽楽精算
東証プライム市場に上場する株式会社ラクスが提供する経費精算システムです。デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査によれば、クラウド型経費精算システム市場で国内累計導入社数No.1を獲得しています。
AI-OCR機能を搭載した専用アプリで領収書を撮影すると、金額、取引先、日付を自動でデータ化します。カスタマイズ性が高く、企業ごとの経費精算ルールに柔軟に対応できる点が特徴です。
弥生シリーズ
弥生株式会社が提供する会計ソフトで、26年連続で年間販売数量ナンバーワンを誇ります。「やよいの青色申告 オンライン」は個人事業主向けの確定申告ソフトで、初年度は無料で利用できます。
「やよいの白色申告 オンライン」は完全無料で利用可能です。スマートフォンアプリ「弥生 レシート取込アプリ」を使えば、レシートや領収書を撮影するだけで金額や日付を自動で読み取ります。初心者でも使いやすいシステム設計が特徴です。
freee会計
freee株式会社が提供するクラウド会計ソフトです。スマートフォンでの使用を前提に設計されており、アプリの使いやすさに定評があります。
領収書をスマートフォンで撮影すると、AIが自動で金額や使用用途を推測し、登録します。確定申告書の作成も、質問に答えていくだけで自動で完成する仕組みになっています。電子帳簿保存法に完全対応しており、スキャンした領収書の原本保管は不要です。
ジンジャー経費
jinjer株式会社が提供する経費精算システムです。ジンジャーシリーズ全体では製品により月額300円〜となっていますが、経費精算システムの利用料金は月額一人あたり500円です。タイムスタンプの付与やOCR機能による領収書の電子化が可能で、電子帳簿保存法に対応しています。
自動仕訳機能により、取引情報の入力や勘定科目への仕訳を自動化できます。スマートフォンから各種申請や承認が可能で、場所を選ばずに経費精算業務を進められます。
アプリ選びのポイント
領収書管理アプリを選ぶ際は、電子帳簿保存法への対応、操作の簡便性、会計ソフトとの連携、コストパフォーマンス、サポート体制などを総合的に判断することが重要です。
電子帳簿保存法への対応
アプリを選ぶ際の最重要ポイントは、電子帳簿保存法への対応状況です。2024年1月から電子取引データの保存が義務化されているため、法令の要件を満たしたシステムを選ぶ必要があります。
なお、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の認証を取得しているソフトウェアは、法的要件を満たしていることになります。
操作の簡便性
日常的に使用するツールであるため、操作が簡単であることは重要でしょう。特にスマートフォンでの操作性に優れたアプリを選べば、外出先や移動時間にも領収書の処理ができます。
無料トライアル期間を設けているサービスも多いため、実際に使ってみて使い勝手を確認することをおすすめします。
会計ソフトとの連携
領収書管理アプリで記録したデータを会計ソフトに取り込めれば、二重入力の手間が省けます。既に使用している会計ソフトがある場合は、そのソフトと連携できるアプリを選ぶことで、業務の効率化が図れるでしょう。
同じ会社が提供する会計ソフトとの組み合わせであれば、データの連携がスムーズです。
コストパフォーマンス
個人事業主にとって、導入コストは重要な検討事項です。無料プランや低価格プランが用意されているサービスも多くあります。
弥生の「やよいの白色申告 オンライン」は完全無料で利用できます。「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料で、2年目以降もセルフプランなら年額10,300円と比較的リーズナブルです。
サポート体制
初めて会計ソフトを使用する場合、充実したサポート体制があると安心でしょう。電話、メール、チャットなど、複数の問い合わせ方法が用意されているサービスが望ましいといえます。
操作マニュアルやヘルプページの充実度も確認しておきたいところです。
領収書管理の実務ポイント
日常の領収書管理をスムーズに行うためには、受領時、月次、年次それぞれのタイミングで適切な処理を行うことが大切です。ここでは実務上のポイントを解説します。
領収書の受領時
領収書を受け取ったら、できるだけ早くアプリに登録することが重要です。時間が経過すると、何の支出だったかを思い出すのに時間がかかります。移動中や待ち時間など、スキマ時間を活用してスマートフォンで撮影し、その場で登録する習慣をつけましょう。
領収書の裏面にメモ書きをしておくことも有効です。特に交際費や会議費など、目的や参加者の記録が必要な経費については、詳細を記録しておくことで、後から確認する際に役立ちます。
例えば、医療機器メーカーの担当者との会議で昼食を取った場合、「○○メーカー△△氏、新型医療機器の商談」といった具体的な内容をメモしておくとよいでしょう。
月次での確認
月末には、その月の領収書がすべて記録されているかを確認してください。クレジットカードの利用明細と照合し、記録漏れがないかをチェックします。
経費の集計を月次で行うことで、経営状況を把握しやすくなります。月次での確認を習慣化すれば、年度末に慌てて記録を整理する必要がなくなるでしょう。
年次決算への準備
確定申告の時期になって慌てないよう、日頃から記録を整備しておきます。領収書のデータ化が完了していれば、確定申告書の作成作業が格段にスムーズになります。会計ソフトを使用していれば、日々の取引記録から自動的に決算書が作成されます。
ただし、期末の棚卸や減価償却の計算など、手動での調整が必要な項目もあるため、余裕を持って準備を進めることが望ましいでしょう。
領収書がない場合の対処法
やむを得ず領収書を受け取れなかった場合や紛失した場合の対処法、レシートでの代用、電子取引の記録方法について説明します。
出金伝票の作成
やむを得ず領収書を受け取れなかった場合や紛失した場合は、出金伝票を作成してください。出金伝票には、日付、支払先、金額、支払内容を記載します。ただし、出金伝票は領収書の代わりとして完全に認められるわけではないため、可能な限り領収書を入手することが原則です。
取引の事実を証明できる他の資料(銀行振込の控え、クレジットカードの利用明細、契約書など)があれば、それらも併せて保管しておきましょう。
レシートでの代用
レシートでも領収書の代わりとして認められます。むしろ、日付、品目、金額が詳細に記載されているレシートの方が、「お品代」としか書かれていない領収書よりも証拠能力が高い場合もあります。
ただし、レシートは感熱紙で印刷されていることが多く、時間が経つと文字が消えてしまう可能性があるため、早めにスキャンするか、コピーを取っておくことが推奨されます。
電子取引の記録
ネットショッピングやクラウドサービスの利用など、オンラインでの支払いも増えています。電子データで受け取った領収書は、電子帳簿保存法に従って電子データのまま保存しなければなりません。
印刷して紙で保管するのではなく、ファイル名に日付や取引先名を含めて整理し、検索可能な状態で保存してください。
まとめ
開業医として事業を営む場合、領収書の適切な管理は必須の業務です。領収書は7年間の保存が必要であり、月別や科目別に整理して保管します。2024年1月からは電子取引データの電子保存が義務化されており、法令への対応も求められます。
領収書管理の効率化には、デジタルツールの活用が効果的です。
本記事で紹介した5種類を含め、アプリを選ぶ際は、電子帳簿保存法への対応、操作の簡便性、会計ソフトとの連携、コストパフォーマンス、サポート体制などを総合的に判断して、自身のニーズに合ったアプリを選ぶことが重要です。
領収書を受け取ったらすぐにアプリに登録する習慣をつけ、月次で記録を確認しましょう。日頃から適切に記録を整備しておけば、確定申告の時期になっても慌てることなく手続きを進められます。
適切な領収書管理は、正確な確定申告を行うための基礎であり、経営状況を把握するための重要な情報源でもあります。デジタルツールを活用して効率化を図りながら、医療機関の健全な運営に役立ててください。
※本記事の内容は、作成時点の制度・規制・規約・市況などの情報を基にして作成しております。改正等により記載内容の実施・実行・対応などが行え場合がございますので予めご了承ください。最新情報に基づいた内容などについては、「ご相談・お問い合わせ」ページからご確認いただけますと幸いです。 |